もうすぐ楽しみなお正月がきますね!
お正月は家族そろっておせちを食べる家も多いですね。
おせちにはいろいろな意味があります。
おせちの由来について考えてみましょう。

「節」とは
お節の「せち」とは1年のうちに何度か行われる特別な年中行事の事です。
仕事を休み、神さまたちにいろいろな食べ物をお供えします。
人々も同じものを食べ、その特別料理をせちの料理
すなわち「おせち」と呼びます。
「節」とは江戸時代から始まります。幕府が制定した五節供(ごせっく)のことで、
1月1日(正月元旦は別格)
1月7日(人日の節供)※じんじつ
3月3日(上巳の節供)※じょうし
5月5日(端午の節供)※たんご
7月7日(七夕の節供)※しちせき
9月9日(重陽の節供)※ちょうよう
現代は、お正月に食べる料理のみをおせちと呼ぶようになりました。
お節料理の由来
おせち料理は、お正月に日々を暮らすお家にお正月の神様である年神様をお迎えしお供えする特別なお料理です。
年神様と一緒に家族そろって食べることで、一年の豊作や家族の安全、健康、幸運を授けてくれると言い伝えられています。
また、お正月の3が日の間はそれを食べる習わしがありました。
普段せわしく毎日働いている家内(おばあちゃんやお母さん)を休ませる意味もあります。
おせち料理のそれぞれの意味
お節料理には保存がきく料理というだけでなく、一つ一つに意味があります。
縁起物を食べて家族の健康と幸福を願いましょう。
おせち料理の基本は、祝い肴三種(いわいざかな)といって、酢の物、焼き物、煮しめです。
この3品とおもちが揃えばおせちの形が整いお正月が迎えられるとされています。
関東では黒豆、かずのこ、たづくりの3種
関西では黒豆、かずのこ、叩きごぼうの3種がそれにあたります。
黒豆

「まめ」は本来は丈夫、健康を意味する言葉なので「まめに働く」などの語呂合わせからも、お節料理には欠かせない一品とされています。
かずのこ
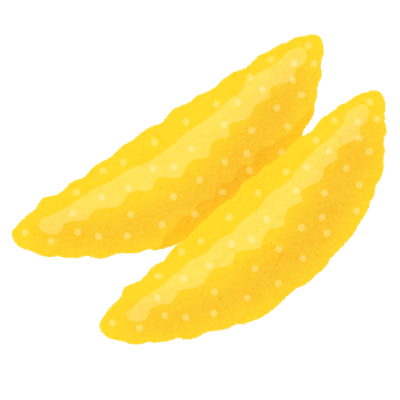
ニシンの卵です。二親から多くの子が出るのは子孫繁栄に繋がるという意味があります。
叩きごぼう

しっかり根を地中に根を張るごぼうを叩いて身を開くことで開運を呼ぶという縁起を担いだものです。
田づくり
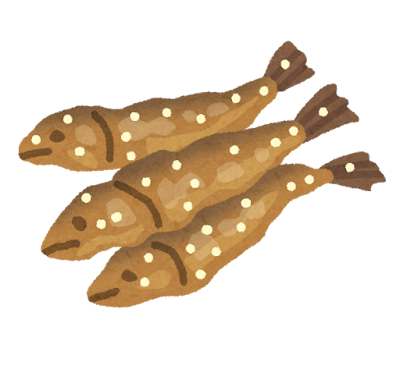
五穀豊穣を願い、小魚を田畑の肥料として巻かれていたことから名づけられています。
小さくてもお頭付きなのでおめでたい一品です。
昆布巻き

「よろこぶ」一家発展の縁起ものです。
紅白かまぼこ
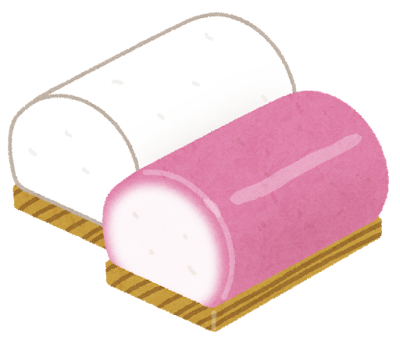
「日の出」紅はめでたさとよろこび、白は神聖な色です。
伊達巻
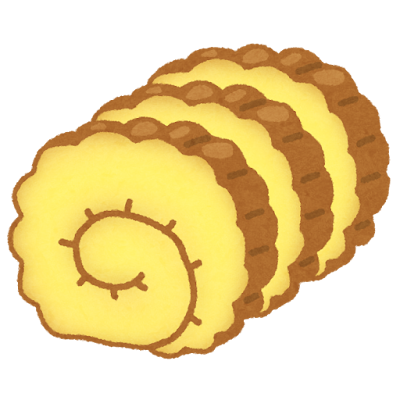
知性の象徴です。むかしの巻物を表しています。華やかな伊達者の意味もあります。
海老
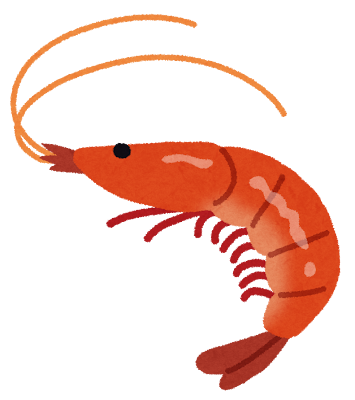
美しく赤く染まり火を通すとキレイに曲がることから「長寿」の縁起物です。
腰がまがるまで長生きとの意味が込められています。



